(認定特定創業支援等事業)証明書の有効期限が切れていた場合の手続き
「認定特定創業支援等事業」を受けて会社設立時に登録免許税を半額にするためには、証明書の提出が必要です。この証明書には有効期限が設定されており、期限切れの場合の対応について以下の通りまとめます。

「認定特定創業支援等事業」(にんていとくていそうぎょうしえんとうじぎょう)は、日本政府や自治体が提供する創業支援の一環として、中小企業や新規事業者の立ち上げをサポートするための制度です。この制度の一つの大きな利点は、会社設立時の登録免許税が半額になる点です。以下、その概要について説明します。
目次
1. 認定特定創業支援等事業とは
2. 支援内容
3. 登録免許税の減免措置
4. 減免を受けるための条件
5. 他の優遇措置
まとめ
1. 認定特定創業支援等事業とは

「認定特定創業支援等事業」は、地方自治体や商工会議所などが提供する創業支援プログラムの一部です。この制度を活用することで、起業家が事業計画や経営の基本的な知識を学ぶ機会が提供され、また、行政手続きにおいても様々な優遇措置を受けることができます。
2. 支援内容
この制度を利用することで、起業家は以下のような支援を受けることができます。
事業計画の作成支援:ビジネスプランの策定を手助けする専門家によるサポート。
経営や財務の知識提供:起業に必要な財務、税務、法務、労務などの基本的な知識を提供。
交流の場の提供:他の起業家や事業家とのネットワーキングイベントやセミナーの開催。
3. 登録免許税の減免措置
最大の利点の一つは、会社を設立する際の「登録免許税」が半額になることです。通常、株式会社設立時には資本金の0.7%を登録免許税として納める必要がありますが、この支援を受けることで、0.35%に軽減されます。例えば、資本金1,000万円の会社を設立する場合、通常の登録免許税は7万円ですが、支援を受けることで3.5万円となります。
4. 減免を受けるための条件
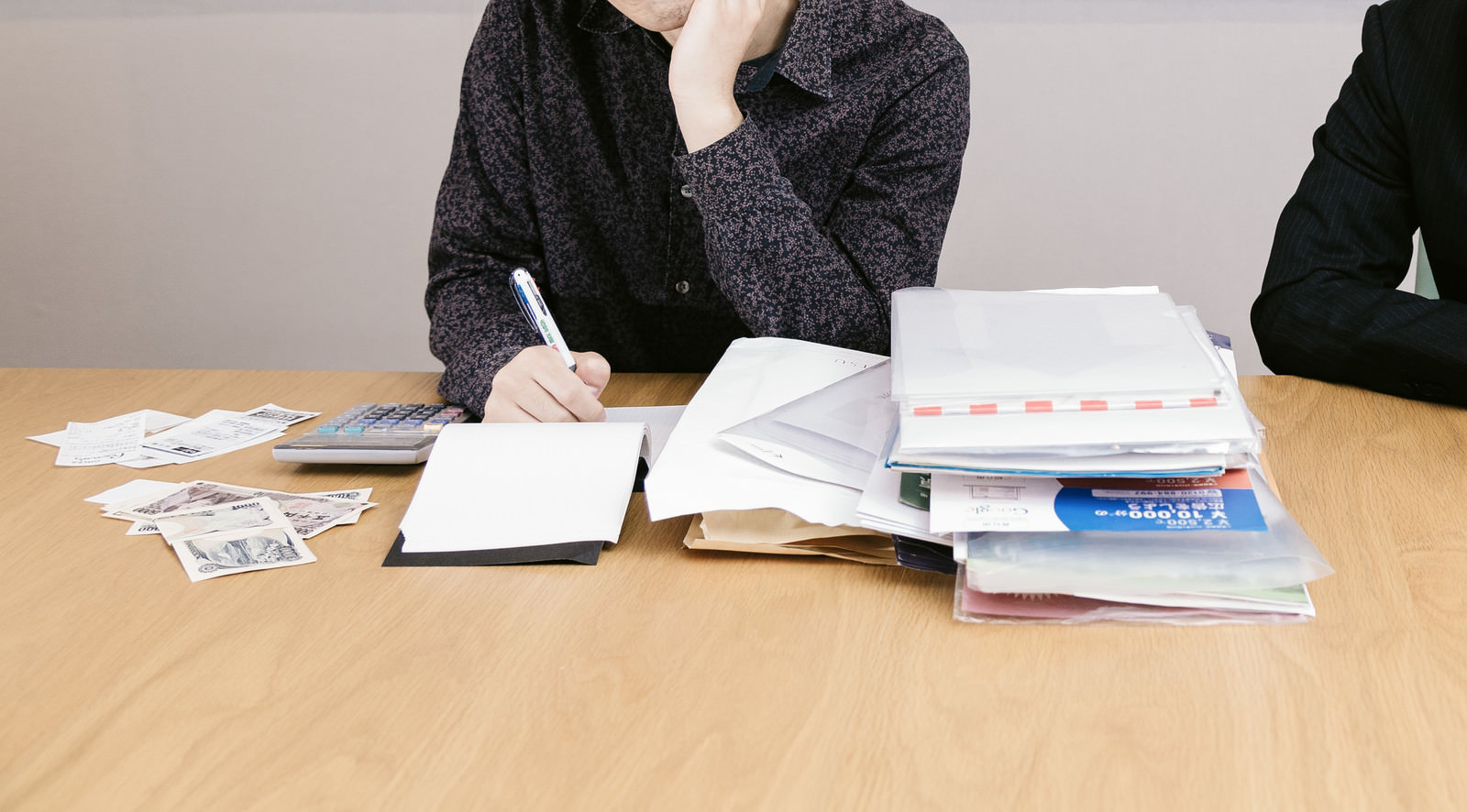
この制度を利用して登録免許税の減免を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
特定の自治体による認定を受けること:創業支援事業を行っている自治体において、その創業支援プログラムを受け、自治体から「特定創業支援等事業を受けた証明書」を発行してもらうこと。
一定の内容の支援を受けること:支援内容として、財務、経営、労務、販路開拓など複数の分野について1か月以上の期間、合計で4回以上の支援を受ける必要があります。
5. 他の優遇措置
「認定特定創業支援等事業」を利用することで、登録免許税の減額以外にも以下のような優遇措置を受けることができます。
信用保証枠の拡大:創業者に対する信用保証枠が拡大され、資金調達がより容易になります。
各種税制優遇:所得税や法人税の軽減措置を受けることが可能です。
まとめ
「認定特定創業支援等事業」は、創業に必要な知識を学びながら、会社設立時のコスト削減や信用保証の拡充などの様々な優遇措置を受けることができる非常に有益な制度です。特に、登録免許税が半額になるという大きなメリットがあるため、これから起業を考えている方は、ぜひこの制度を活用して効率的なスタートを切ることを検討してみてください。
利用を検討する場合は、自治体のホームページや商工会議所などで詳細を確認し、必要な手続きや支援プログラムへの参加を進めることが重要です。

「認定特定創業支援等事業」を受けて会社設立時に登録免許税を半額にするためには、証明書の提出が必要です。この証明書には有効期限が設定されており、期限切れの場合の対応について以下の通りまとめます。
「認定特定創業支援等事業」(にんていとくていそうぎょうしえんとうじぎょう)は、日本政府や自治体が提供する創業支援の一環として、中小企業や新規事業者の立ち上げをサポートするための制度です。この制度の一つの大きな利点は、会社設立時の登録免許税が半額になる点です。以下、その概要について説明します。
2026年度末をもって、長年企業間の取引に用いられてきた手形・小切手の利用が廃止されることが決定しました。この変革は、デジタル化の進展と効率化を目指す金融業界の動きの一環として行われます。本記事では、全国銀行協会の情報を基に、手形・小切手の廃止の背景や影響、今後の課題について詳しく解説します。
日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。