相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年4月16日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
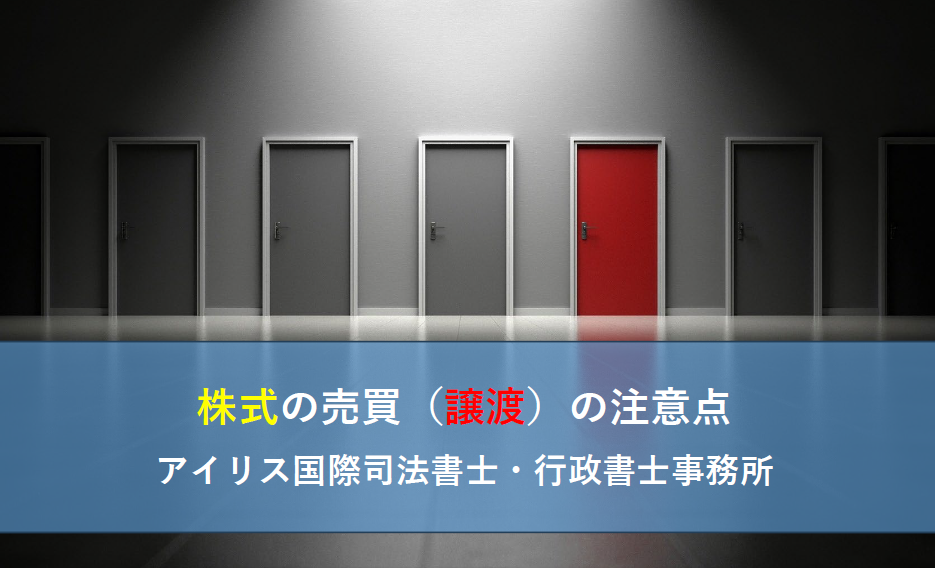
先日の問い合わせで、設立した会社の株主(当初から存在する株主)が、当該株式を手放したいという問い合わせがありました。売り先は、関連会社が買い取るということになるとのことでした。単純な売買だけで考えればいいのでしょうか?それでは、解説します。
目次
1.今回の事例
2.株式の売買で注意すべき点
3.まとめ
1.今回の事例

問い合わせのあった会社の代表は、ほかにもいくつかの会社を経営しており、その中の1社の株主の保有する株式を別会社が引き取る(買いとる)ということになったみたいです。
関連会社すべて株式には譲渡制限規定が設けられており(つまり非公開会社)、株式を譲渡するには「株主総会の承認」が必要となります。また、当該株主のほかにも、当該会社の株主が存在しています。
問い合わせ内容は、どのような対応が必要なのかという点でした。
※株式保有率によるM&A等の場面で問題となる株式譲渡による経営権関連の話は、今回はないということで進めていきます。
2.株式の売買で注意すべき点
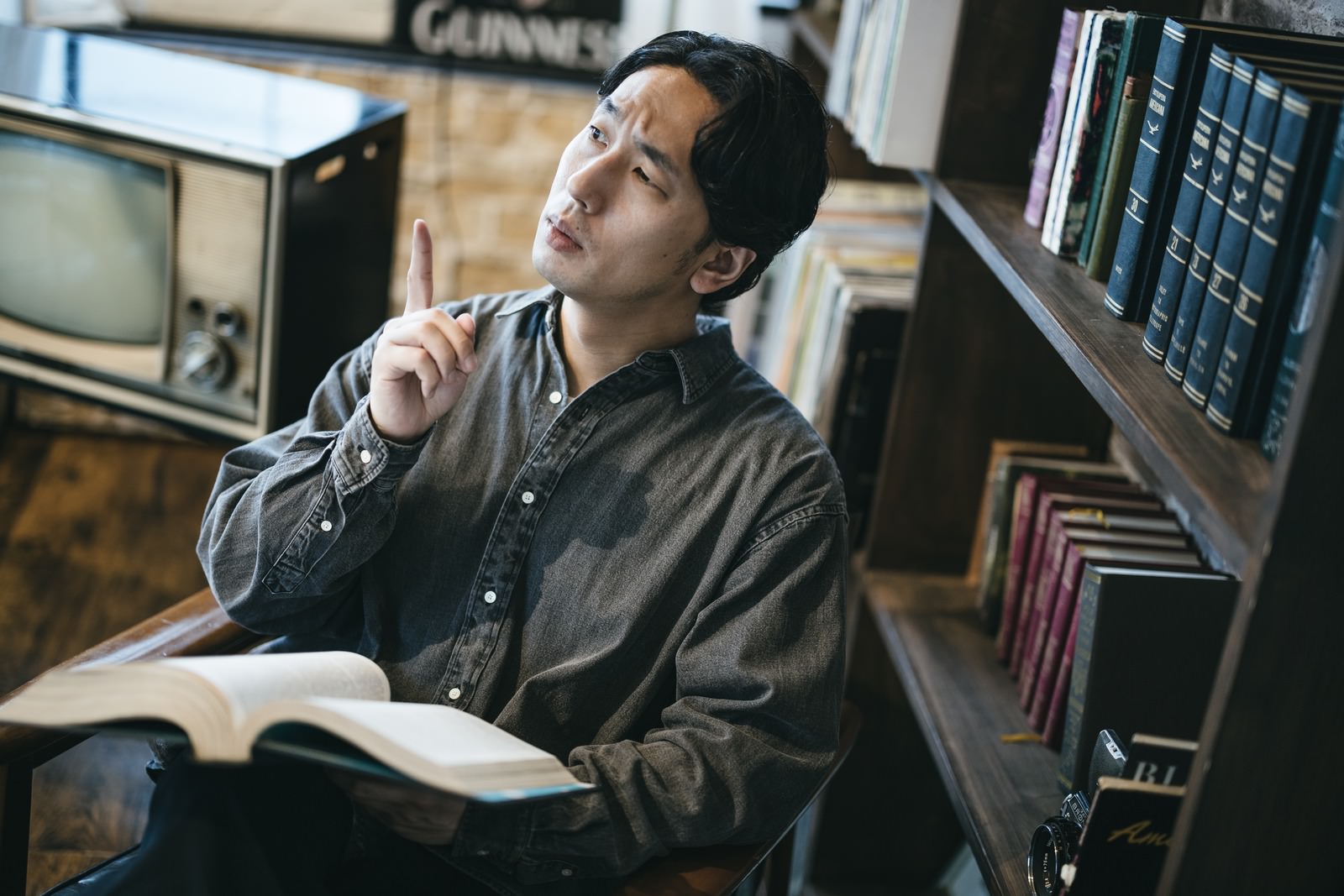
①会社の親子関係
原則、子会社は親会社の株式を取得してはいけません。(会社法135条1項)
例外として以下の場合、子会社による親会社の株式を取得することができます。
㋐他の会社(外国会社を含む)の事業全部を譲り受ける際に紛れ込んだ親会社の株式
㋑合併後消滅する会社から引き継いだ親会社の株式
㋒吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する
㋓新設分割により他の会社から親会社株式を承継する
㋔その他法務省令で定める場合(会社施行規則23条参照)
となっており、子会社が親会社の株式を取得するにあたっては、今回のように買い取るということはできませんが、親会社が子会社の株式を取得することは可能です。
➁譲渡制限株式の譲渡の承認決議
譲渡制限株式の譲渡等について、株式会社が承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければなりません。(会社法139条1項本文)譲渡等承認機関として、定款に別段の定めをすれば、その期間での承認決議となります。(会社法139条1項但書)
株主が譲渡したいと申し出ているのに、会社が承認決議をしない場合、「承認みなし」となる場合があります。
㋐譲渡等承認請求の日から2週間以内に承認するか否かの承認通知がなされなかった場合
㋑株式会社が譲渡等の証人をしない旨の決定通知をした場合、その決定通知の日から10日以内に、指定買取人による買取の通知がなされず、かつ、その決定通知から40日以内に株式会社による買取の通知がなされなかった場合
などが挙げられます。
③株券を発行している場合と発行していない場合の対抗要件を備えること
㋐株券を発行している場合 意思表示+株式を相手方に交付(会社法128条本文)
(株式会社に対する対抗要件)株主名簿への記載・記録(会社法130条2項)
(第三者に対する対抗要件)株式の占有(会社法130条2項)
㋑株券を発行していない場合 意思表示のみ
(株式会社に対する対抗要件)株主名簿への記載・記録(会社法130条1項)
(第三者に対する対抗要件)株主名簿への記載・記録(会社法130条1項)
3.まとめ
今回のケースのように関連会社が、株式を譲渡により取得する場合、親子関係が重要になってきます。
譲渡制限株式の譲渡の場合、譲渡承認決議を経たうえで、証人の通知を行い、株主名簿への記載・記録をすることで、株式会社への対抗要件を具備することになりますが、株券を発行している場合には、第三者要件として「株券の占有」が必要となります。
司法書士の登記手続きに関してですが、発生しません。ただし、譲渡承認の幹部主総会決議の議事録を作成してほしいですとか、株式譲渡の契約書の作成については、有償で対応させていただいております。

令和7年4月16日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を相続しない旨を家庭裁判所に申し立てる手続きであり、相続放棄をした者は民法上、初めから相続人ではなかったこととみなされます。しかし、相続放棄をした場合でも、相続税法上の取り扱いには注意が必要です。特に、相続放棄をした元相続人が生命保険金を受け取る場合や、遺贈を受ける場合における相続税の扱いについては、いくつかの重要なポイントがあります。本記事では、相続放棄した相続人の取り扱いに関連する相続税法上の問題点として、①生命保険金に関する非課税規定の適用、➁相続放棄した元相続人が遺贈を受ける場合の相続税2割加算について解説します。
遺産分割協議は、相続人間で相続財産をどのように分割するかを合意する重要な手続きです。しかし、合意後に様々な理由からその協議を解除する必要が生じる場合もあります。遺産分割協議の解除は、法律上の効力が生じた後であっても可能な場合がありますが、その条件や影響については慎重に検討する必要があります。本記事では、遺産分割協議の解除に関する基本的な知識と手続きについて解説し、実際に協議を解除する際に留意すべきポイントを探ります。
相続が発生すると、遺産分割協議を行い、相続人全員が合意した上で遺産分割協議書を作成することが一般的です。しかし、時折、いきなり遺産分割協議書と称する書面が送られてきて、「署名押印し、印鑑証明書を添えて返送してください」といった依頼が届くことがあります。このような状況では、何も考えずに書面に署名・押印するのは危険です。本記事では、突然の遺産分割協議書送付における問題点と、その際の適切な対応について、外部情報を参照しながら解説します。