相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
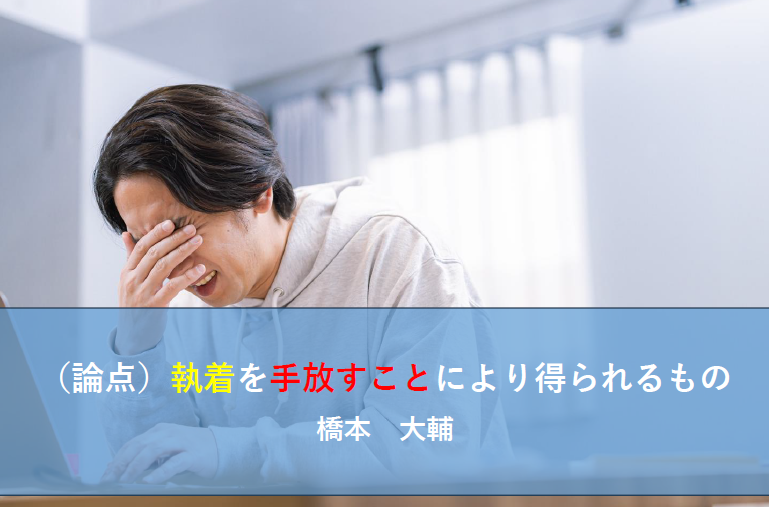
「物事がうまくいかない場合、『執着』を手放すことで、自分に『空き』ができ、新たな事柄を取得できる」という考え方は、古くから多くの哲学や宗教、心理学において重要なテーマとされています。この考え方の背景には、執着が私たちの心や思考を縛りつけ、視野を狭めることがあるという認識があります。ここでは、執着を手放すことの重要性と、それがどのように新たなチャンスや可能性をもたらすのかについて考えてみます。
目次
1. 執着とは何か?
2. 執着がもたらす影響
3. 執着を手放すことの意義
4. 心の「空き」を作る方法
5. 新たな事柄を取得するための心構え
6. 結論
1. 執着とは何か?

執着とは、ある特定の物事や人間関係、考え方に強くこだわり、それを手放すことができない状態を指します。これは、過去の成功体験や未練、あるいは未来への不安や期待に基づく場合が多いです。たとえば、あるプロジェクトが成功しなかった場合、その失敗に対する執着は、私たちの心を過去に縛り付け、前に進むことを妨げます。また、特定の目標に固執するあまり、他の可能性を見逃すこともあります。
2. 執着がもたらす影響
執着がもたらす影響は、多岐にわたります。まず、執着はストレスや不安を増幅させる要因となります。何かに固執することで、その物事が思い通りにいかない場合、強い焦燥感や絶望感を感じることがあります。また、執着は創造性や柔軟性を奪い、私たちが新しいアイデアや視点を受け入れることを困難にします。これにより、物事が行き詰まったり、新たなチャンスを見逃したりすることが多くなります。
3. 執着を手放すことの意義
執着を手放すことは、心の余裕を取り戻すための第一歩です。執着を手放すことで、私たちは過去や未来に縛られず、今この瞬間に集中できるようになります。これにより、私たちの心には「空き」が生まれ、新たな情報やアイデア、チャンスを受け入れる余地ができるのです。たとえば、新しいプロジェクトや人間関係に対してオープンな姿勢を持つことで、これまで気づかなかった可能性に気づくことができます。
4. 心の「空き」を作る方法

心の「空き」を作るためには、まず自分自身を見つめ直し、何に対して執着しているのかを認識することが重要です。その上で、執着を手放すための具体的な方法を実践してみましょう。たとえば、瞑想やマインドフルネスといった心を静める手法は、執着を手放し、心の空きを作るのに役立ちます。また、自分の価値観や目標を見直し、本当に大切なことに焦点を当てることも有効です。
しかし、現状維持で増やそうとしてもそう増えるものではありませんので、時として不要と感じるものは捨ててみる習慣が必要かもしれません。
5. 新たな事柄を取得するための心構え
執着を手放し、心に空きを作ることで、新たな事柄を受け入れる準備が整います。しかし、新しいものを取得するためには、柔軟な心とオープンな態度が必要です。これには、未知のものに対する恐れを克服し、新しい経験やチャレンジを受け入れる勇気が求められます。また、失敗を恐れず、試行錯誤を繰り返すことで、次第に新しい可能性が見えてくるでしょう。
6. 結論
物事がうまくいかない時に執着を手放すことは、新たなスタートを切るための重要なステップです。執着を手放すことで、心に空きが生まれ、これまで見えていなかったチャンスや可能性を見つけることができます。人生には変化がつきものであり、その変化に柔軟に対応するためにも、執着を手放し、新しいものを受け入れる姿勢を持つことが大切です。最終的には、自分自身の成長と充実した人生を築くために、執着を手放し、心の空きを作ることが必要不可欠です。
そのためにも人生の棚卸を定期的にしましょう。

令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
共同通信の記事によると、2026年から本格化する「電子戸籍」の活用では、マイナンバーカードや新たに導入される「マイナ免許証」が重要な役割を果たすことが期待されています。具体的には、戸籍情報の取得や提供がデジタルで行われることにより、これまでの紙の戸籍謄本の提出が不要になるという利便性が強調されています。
2025年5月より、戸籍氏名のフリガナの通知制度が日本全国で開始されます。この制度は、氏名の読み方に関する誤解やトラブルを減らし、行政手続きや民間サービスにおける個人認識の正確性を向上させる目的で導入されます。近年、日本では多様な名前の読み方が増えており、フリガナが記載されていないことが、正しい読み方の確認を困難にしていました。この問題を解決するため、政府は戸籍にフリガナを記載する制度を導入することとなりました。本稿では、この制度が導入されるに至った経緯と、具体的な手続きの流れについて詳しく説明します。
不動産登記のスマート化が進む中、登記名義人となる方の「メールアドレスがない場合はどうすればよいのか?」といったご相談を多くいただくようになりました。特に令和7年4月21日からの改正により、検索用情報(メールアドレス・よみがな・生年月日)の提出が義務化され、登記実務に大きな影響を与えています。この記事では、改正内容の要点と、メールアドレスを持たない方のための具体的な申請方法、そして今後の登記制度の方向性について分かりやすく解説いたします。