相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年4月16日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

司法書士試験の受験生にとって、勉強や日常生活において「変えられるもの」と「変えられないもの」を見極めることは、合格への重要なステップです。特に長期にわたる受験生活では、集中力や精神的な安定を保つために、自分の周りの環境や人間関係に注意を払う必要があります。ここでは、司法書士受験生に向けて、「変えられないもの」と「変えられるもの」の違いについて考え、勉強や生活にどう活かすべきかを探ります。
目次
1. 変えられないもの:「過去」と「他人」
2. 害になる人との距離を置く選択肢
3. 変えられるもの:「未来」と「自分」
4. 害になる他人との関係が「未来」と「自分」に与える影響
まとめ
1. 変えられないもの:「過去」と「他人」

まず、司法書士試験に限らず、人生全般において変えられないものの代表的な例が「過去」と「他人」です。「過去」は文字通り、過ぎ去った時間や出来事を指し、どれだけ悔やんでも、やり直すことはできません。たとえ過去に何か後悔する出来事があったとしても、その事実を変えることはできないため、未来に目を向けることが重要です。例えば、過去の失敗や模試の点数が思わしくなかった経験も、それ自体を変えることはできませんが、そこから学んで今後の対策を講じることで、未来に生かすことができます。
もう一つ変えられないのが「他人」です。私たちは他人の行動や考え方を直接的に変えることはできません。周囲の人々がどう振る舞うか、どう考えるかは、その人自身の選択であり、受験生自身がコントロールすることはできません。特に受験期間中には、友人や家族、同僚など、さまざまな人との関わりがありますが、すべての人が必ずしも自分にとって良い影響を与えるわけではありません。
2. 害になる人との距離を置く選択肢
受験生にとって最も大切な資源は「時間」と「集中力」です。これらを妨げる要因として、害になる人間関係が挙げられます。例えば、否定的な発言を繰り返す友人や、必要以上にプレッシャーをかける家族、または単に勉強の邪魔をするような環境にいる人々は、あなたの成績向上や合格への道を阻害する可能性があります。こうした人間関係は、できるだけ距離を置き、自分の目標達成に集中することが大切です。
「害になる」と感じる人との関係を断つことは、時に難しいかもしれませんが、受験生活では自己防衛の一環として重要な選択肢です。他人の意見や感情に振り回されてしまうと、学習の質が下がり、合格に必要な努力を妨げる要因となってしまいます。ここで意識すべきことは、あなた自身の目標にフォーカスすることであり、もし他人がその目標を妨げるようであれば、一時的にでも距離を取ることが最善です。
3. 変えられるもの:「未来」と「自分」

一方で、受験生が自らの力で変えられるものも存在します。それが「未来」と「自分」です。未来は、これからの行動や選択によって大きく変わるものです。例えば、これからの勉強方法やスケジュールの立て方、試験に向けた対策の充実度によって、合格への道は開かれていきます。過去は変えられませんが、未来は自分の手で創り上げることができるのです。
そして、「自分」もまた変えられるものです。具体的には、習慣や思考パターン、勉強に対する姿勢などが挙げられます。受験勉強は長い期間にわたり、途中で疲れや焦りが生じることもあるでしょう。しかし、そんな時こそ「自分を変える」という意識が重要です。例えば、毎日の学習に対するモチベーションをどう維持するか、プレッシャーをどう乗り越えるか、計画通りに進まない時にどう対応するかなど、自分自身を見直し、必要な部分を変えていくことで、合格に向けた道を整えることができます。
4. 害になる他人との関係が「未来」と「自分」に与える影響
ここで気をつけたいのは、害になる他人との関係を続けることで、変えられるはずの「未来」と「自分」が損なわれる可能性があるという点です。もし、害を及ぼすような人間関係に執着してしまうと、それはあなた自身の成長や目標達成の大きな阻害要因となってしまいます。
例えば、周囲からのネガティブな影響を受け続けることで、自己肯定感が低下し、勉強に対する意欲が減少することがあります。また、他人の期待やプレッシャーに押しつぶされ、必要以上にストレスを感じることもあるでしょう。こうした状況では、たとえどれだけ自分を変えようと努力しても、外的な要因が影響を与え続ける限り、未来を変えるための行動が妨げられてしまいます。
そのため、司法書士試験という大きな目標を達成するためには、まず自分にとって害になる関係を見直し、必要であればそれを断ち切る勇気を持つことが重要です。受験生活は自己との闘いであり、他人との関係がその闘いの足を引っ張るようであれば、思い切って距離を置くことが、自分の未来を守る一歩となります。
まとめ
司法書士試験を目指す受験生にとって、「過去」や「他人」といった変えられないものにこだわるよりも、「未来」や「自分」といった変えられるものに集中することが合格への近道です。特に、害になる他人との関係を見直し、必要に応じて距離を置くことは、未来の自分を守るために重要な選択肢です。試験勉強は、周囲の影響を受けやすい時期ですが、自分自身の目標に向かって突き進むことで、確実に未来を変えることができるのです。
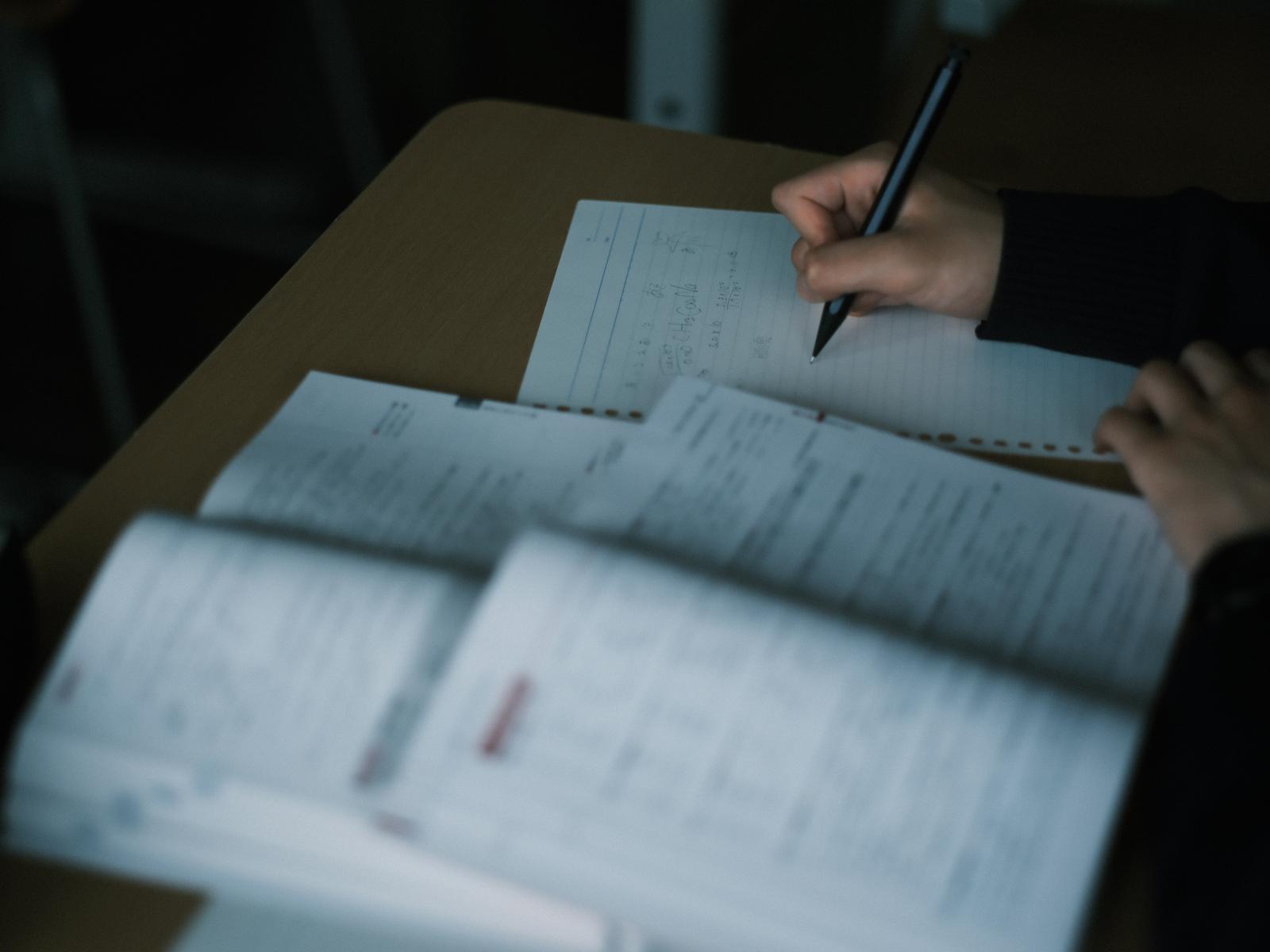
令和7年4月16日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を相続しない旨を家庭裁判所に申し立てる手続きであり、相続放棄をした者は民法上、初めから相続人ではなかったこととみなされます。しかし、相続放棄をした場合でも、相続税法上の取り扱いには注意が必要です。特に、相続放棄をした元相続人が生命保険金を受け取る場合や、遺贈を受ける場合における相続税の扱いについては、いくつかの重要なポイントがあります。本記事では、相続放棄した相続人の取り扱いに関連する相続税法上の問題点として、①生命保険金に関する非課税規定の適用、➁相続放棄した元相続人が遺贈を受ける場合の相続税2割加算について解説します。
遺産分割協議は、相続人間で相続財産をどのように分割するかを合意する重要な手続きです。しかし、合意後に様々な理由からその協議を解除する必要が生じる場合もあります。遺産分割協議の解除は、法律上の効力が生じた後であっても可能な場合がありますが、その条件や影響については慎重に検討する必要があります。本記事では、遺産分割協議の解除に関する基本的な知識と手続きについて解説し、実際に協議を解除する際に留意すべきポイントを探ります。
相続が発生すると、遺産分割協議を行い、相続人全員が合意した上で遺産分割協議書を作成することが一般的です。しかし、時折、いきなり遺産分割協議書と称する書面が送られてきて、「署名押印し、印鑑証明書を添えて返送してください」といった依頼が届くことがあります。このような状況では、何も考えずに書面に署名・押印するのは危険です。本記事では、突然の遺産分割協議書送付における問題点と、その際の適切な対応について、外部情報を参照しながら解説します。