相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
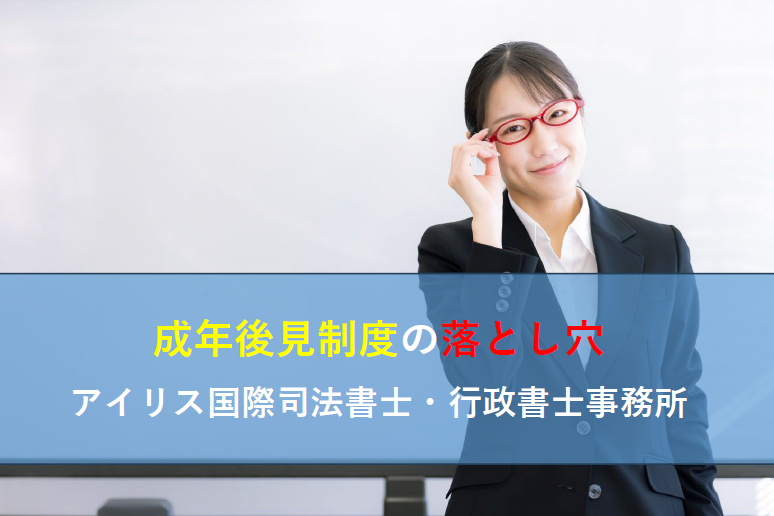
認知症になった後の財産管理制度として、「成年後見制度」があります。現在、成年後見制度をより使いやすい制度にすべく見直しを行っている最中ですが、家族を成年後見人にしたことで事件が発生しております。成年後見制度の成年後見人は、実質、本人に代わって財産管理をはじめ様々な権限が与えられます。専門家を指定した場合、報酬が発生するため、家族を成年後見人に指定して申請する方も多いかと思います。今回はこの事件について解説したいと思います。
目次
1.事件の概要
2.問題が引き起こす連鎖反応
3.まとめ
1.事件の概要

(令和6年2月27日テレビ静岡記事引用)
「成年後見人の立場を悪用して、認知症の母親の口座から現金 約890万円を引き出したとして42歳の派遣社員の男が逮捕されました。
業務上横領容疑で逮捕されたのは千葉県市川市に住む契約社員の男(42)で、認知症になった実の母親の成年後見人に選任されていた2020年7月から2021年11月までの間、自らが使用する目的で母親の口座から40回以上にわたって現金 計890万円を引き出した疑いです。
警察によると、男は累計の出金額が多額だったため2021年11月に成年後見人を解任されていて、その後、後見人に選任された弁護士が刑事告訴していました。
男は容疑を認めていて、警察が犯行の動機や金の使い道などを調べています。」(記事引用終わり)
記事を見る限り、成年後見人に選任された家族が、被成年後見人(本人)の口座の管理を任されているのも関わらず、自分で使用する目的で預金を使い込んだというものです。
2.問題が引き起こす連鎖反応
以前、他士業の方から、成年後見の申し出を出してほしいとの話をいただきましたが、断った経緯があります。その理由として、成年後見人として指定者されていたのが、家族だったからです。財産は比較的少ない方だったのですが、リーガル登録(成年後見人としての講習を受け、登録をしている)されている司法書士の先生にお願いするようにアドバイスしました。財産の多い少ないの問題でなく、専門家でない成年後見人が選任された場合には、上記のようなことが発生しうるからです。ただし、成年後見人を選任するのは、あくまでs家庭裁判所であり、指定していたからと言ってその方が選任されるわけではありません。その場合には、指定されていた家族からクレームの電話が来ます。決定内容に不服があれば、当然控訴なども考えられますが、この家庭裁判所の判断については、控訴等は受け付けてくれません。対象外になっているためです。
逆に、このようにクレームの電話が来るケースについては、「よからぬことを考えていたのでは?」と勘ぐってしまいます。
このように使い込みが発生した場合、家族であっても刑事事件として告訴されます。
そして、他に相続人がいた場合、問題はこれだけでは収まりません。将来発生する相続で得られるはずだった財産について、民事訴訟を起こされる可能性もあります。こうなると家族間の関係は、修復不可能になるでしょう。

3.まとめ
財産を管理する成年後見人は、報酬を支払ってでも専門家にするのか、それとも家族にすればいいのかという問題は付きまといます。ただし、家族がなった場合でも、家庭裁判所で選任した後見監督人が選任される場合がありますので、結局報酬が発生する可能性もあります。
このような事件の発生を抑止する意味でも、専門家にお願いしたほうがいいのではと考えてしまいます。一方で、財産管理の手法で、家族と専門家の成年後見人との間で意見の違いが発生する場合もあります。
いずれにしても、成年後見制度を利用する場合には、家族で話し合い、家族の中から指定者を選ぶ場合にも、慎重に判断すべきだと思います。


令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
開業して3年目を迎える司法書士として、初年度は積極的に営業活動を行いましたが、主に「不当誘致」の問題に悩まされ、成果を上げることができませんでした。その後、紹介を基盤とする営業へ転換し、異業種の士業と連携することで案件が増加しました。一方、インターネット集客にも力を入れており、現在の課題はコンバージョン率の改善です。これからも計画的に改善を進め、さらなる成長を目指します。
自己分析や企業戦略において、SWOT分析は広く利用されており、自分や組織の強み(Strengths)と弱み(Weaknesses)を把握することが目的とされています。しかし、SWOT分析を通じて弱みを強みに変えることが必須ではないという新しい視点が注目されています。むしろ、強みをさらに伸ばし、弱みは適切に補完することがより効果的であると言われています。本稿では、SWOT分析を活用する際に、「弱みを強みに変える」ことに固執するのではなく、強みを強固にすることの意義や、弱みを補完するアプローチについて考察します。
共同通信の記事によると、2026年から本格化する「電子戸籍」の活用では、マイナンバーカードや新たに導入される「マイナ免許証」が重要な役割を果たすことが期待されています。具体的には、戸籍情報の取得や提供がデジタルで行われることにより、これまでの紙の戸籍謄本の提出が不要になるという利便性が強調されています。