相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
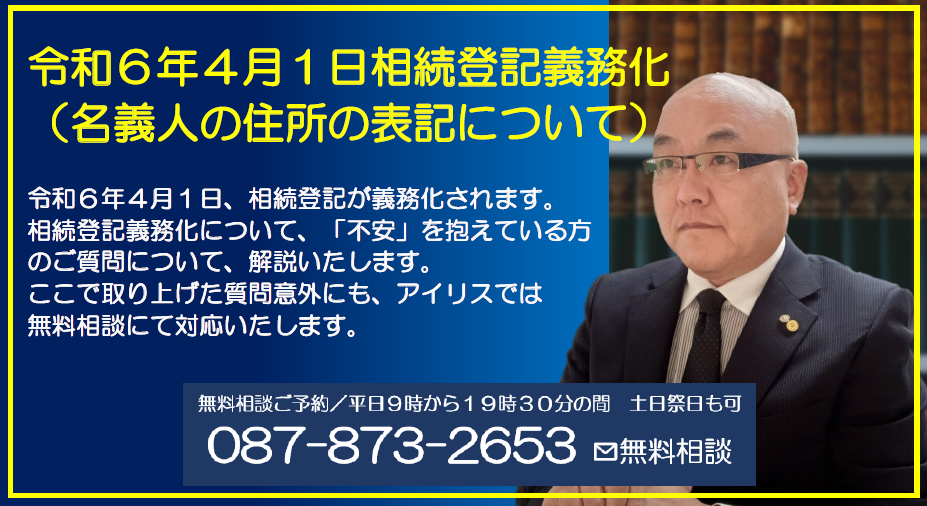
先日、住民票の住所に「○〇方」という表記がありました。相続登記のような名義人を変更する場合、申請の際に住民票を添付するのですが、果たして住民票に記載されている表記すべてを名義人の住所として記載する必要があるのかについて解説したいと思います。
目次
1.住民票の表記
2.アパート・マンション・〇〇方
3.まとめ
1.住民票の表記
最近、住所に関する質問や間違いが多いので、少し解説したいと思います。

「〇丁目」の表記ですが、「一丁目(漢数字)」「1丁目(アラビア数字)」のどちらで登記すればいいのでしょうか?この場合は、必ず漢数字になります。たまに、住民票上の住所は「1丁目」なのに間違っているとおっしゃる方がいらっしゃいますが、「××〇丁目」は固有名詞と解されている(例えば「錦町二丁目」)ので漢数字を使うようです。
ここ何年かで町名がアラビア数字で表記されている住民票や印鑑証明書をたまに見かけることがありました。確かに、役所の文書の表記が正しいと思ってしまうのは、当然と言えば当然なのかもしれませんね。
2.アパート・マンション・〇〇方
マンションの住民票の住所の表記は、少し特徴があります。住所の表記として、「〇番〇号××マンション101号」「〇番〇-101号××マンション」のように、「号」が来る位置が違ったり、マンション名があったりなかったり、部屋番号があったりなかったりしています。現に私の住まいも「〇番〇-101号××マンション」という表記になっています。
これがアパートと呼ばれる建物になりますと、「〇番〇号××アパート」という表記が一般的です。過去に登記した資料を確認すると、アパートの場合は確かにこのような表記になっています。
それでは、マンションやアパートの名義変更の際に登記すべき住所の表記はどのようなものになるのでしょうか。実務では、「~号」までは必ず登記しなければならず、それ以下は任意で登記できることになっています。ですので、「〇番〇-101号」なのに「〇番〇号」と登記することはできません。必ず部屋番号まで含めた〇―101号と登記しなければならないわけです。末尾のマンション名は登記してもしなくても構いません。
最後に、「○〇方」という表記の場合には、どのようにすればいいのかお話をしたいと思います。この「○〇方」ですが、役所への申し出によって表示することや表示しないことができます。そのため、住所としては必ず表記しなければならないものではありません。よって、登記も同じということになりますので、住民票に(住所)○〇方の場合、(住所)のみの表記で登記申請しても受理されます。
3.まとめ
まとめますと、
①「〇丁目」の表記は、不動産登記を申請する場合は漢数字での表記となります。
➁「〇番〇号」までが不動産登記の住所表記しなければならない範囲となるため、アマパート、マンション名の表記は省略することができます。ただし、部屋番号が号の表記に含まれる場合には、部屋番号までが登記の際に表記しなければならない範囲となります。
③(住所)「〇〇方」の場合、「〇〇方」の表記は任意となります。
住民票や印鑑証明書に記載されている住所を全部登記に反映しなければならないと思われている方もいますが、実は上記のように、省略することも可能な部分もあります。


令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続が発生した際、不動産の所有権移転を行うためには、相続登記を行う必要があります。一般的な相続登記では、父親が死亡し、配偶者と子供が相続人となるケースがよく見られます。この際に必要となる添付書類は、法定相続分による登記と、二次相続対策として子供に所有権を移転する場合で異なります。特に二次相続に備えるための所有権移転には慎重な準備が必要です。本稿では、それぞれのケースでの必要な書類を整理し、どのように進めるべきかを解説します。
開業して3年目を迎える司法書士として、初年度は積極的に営業活動を行いましたが、主に「不当誘致」の問題に悩まされ、成果を上げることができませんでした。その後、紹介を基盤とする営業へ転換し、異業種の士業と連携することで案件が増加しました。一方、インターネット集客にも力を入れており、現在の課題はコンバージョン率の改善です。これからも計画的に改善を進め、さらなる成長を目指します。
自己分析や企業戦略において、SWOT分析は広く利用されており、自分や組織の強み(Strengths)と弱み(Weaknesses)を把握することが目的とされています。しかし、SWOT分析を通じて弱みを強みに変えることが必須ではないという新しい視点が注目されています。むしろ、強みをさらに伸ばし、弱みは適切に補完することがより効果的であると言われています。本稿では、SWOT分析を活用する際に、「弱みを強みに変える」ことに固執するのではなく、強みを強固にすることの意義や、弱みを補完するアプローチについて考察します。